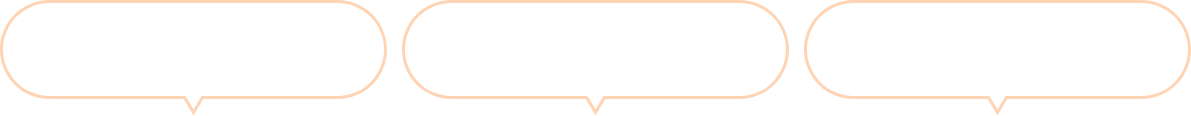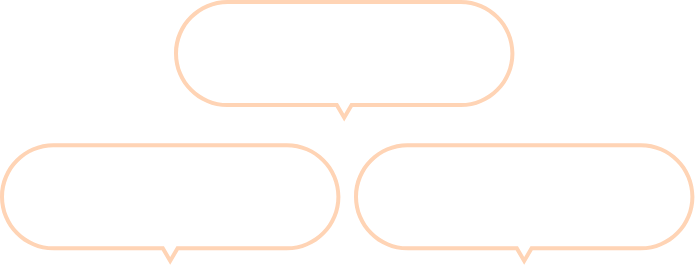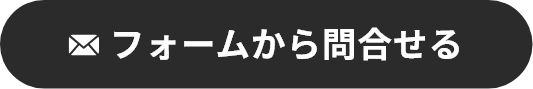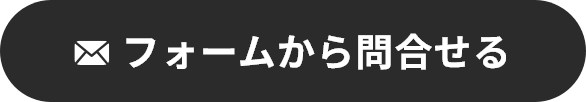マンガ制作で商品やサービスを分かりやすく伝える
2025/09/09
自社の商品やサービスを、WEBサイトやSNSを通じて発信している企業は多いと思います。しかし実際に「自社の魅力が十分に伝わっているか」と問われると、首をかしげる担当者も少なくないのではないでしょうか。文章で丁寧に説明してもユーザーに読まれなかったり、専門的な内容だと理解してもらえなかったりする課題は多くの企業が抱えています。
その解決策の一つとして、今注目を集めているのが「マンガ制作」です。日本人にとって馴染み深いマンガは、単なる娯楽の域を超え、ビジネスの現場でも強力なマーケティング手法となっています。ここでは、発注を検討する企業の視点から、マンガ活用のメリットや活用方法、制作時のポイントを整理し、さらに実際の事例も紹介します。
Contents
マンガを導入する企業が増えている理由
1. 一目で伝わる
商品やサービスの特徴を説明する際、文章や写真だけでは「理解してもらうまでの時間」がかかります。一方、マンガはイラストとセリフで直感的に伝えられるため、初見のユーザーでも短時間で理解可能です。
2. 感情に訴えられる
マンガはストーリー仕立てで「困っている主人公が商品を使って課題を解決する」流れを描けます。ユーザーは主人公に感情移入しやすく、自分事として商品やサービスを捉えるきっかけになります。
3. SNSでの拡散性
InstagramやX(旧Twitter)では、テキストよりも画像やマンガが圧倒的に拡散されやすい傾向があります。広告色を抑えつつストーリー形式で発信すれば、自然にシェアされ、認知拡大にもつながります。
活用シーン別の図表テンプレート
この表は活用シーンや課題別に分かりやすくまとめました。貴社の課題を解決するヒントになるものはございましたか?
| 活用シーン | 従来の説明手法(文章・写真) | マンガ活用時の効果 |
|---|---|---|
| サービス説明 | 難解で離脱しやすい | 視覚的に理解しやすい、最後まで読まれる |
| 商品PR | 写真だけでは差別化が難しい | キャラやストーリーで記憶に残る |
| 採用活動 | 求人票の印象が薄い | 志望動機を刺激、応募数増加 |
| 社内教育 | マニュアルが読まれない | 楽しく学べて定着率向上 |
発注企業が得られる具体的な効果
サービス理解の促進
専門性が高く複雑なサービスでも、マンガで説明すれば短時間で理解されやすくなります。
問い合わせ・購入率の向上
「読む → 共感 → 行動」という流れを作りやすいため、従来より高いCVR(コンバージョン率)が期待できます。
主人公が抱える課題と自分の課題が一致している場合などは効果を期待しやすいといえるでしょう。
採用強化
採用ページにマンガを掲載すると、会社の雰囲気や働くイメージが伝わりやすく、応募者数や質の向上につながります。
また、採用から一人前に育つまでのストーリーなどは不安の払しょくにも役立ちます。
社内教育にも活用可能
外部向けだけでなく、社内研修資料やマニュアルをマンガ化する事例も増えており、学習効果を高められます。
ケーススタディやインシデントのあるあるなども実体験した感覚で学ぶことが可能です。
マンガ活用の具体的な可能性
活用例1:不動産会社(BtoCサービス)
相続不動産の売却支援サービスを紹介する際に、マンガを活用する方法があります。
「なにから始めたらよいかわからない」と悩む人物を主人公にしたストーリーを描き、解決までの流れを視覚的に伝えることで、安心感を与えることが可能です。
また、相続不動産を放置した場合のリスクや空き家問題など、社会的なテーマをストーリーの中で触れることで、サービス紹介に加えて社会的意義を訴求することも期待できます。
活用例2:ソフトウェア開発会社(BtoBサービス)
自社が提供するクラウド型業務システムやSaaSサービスを紹介する際に、マンガを利用するケースも考えられます。
営業担当者や企業の担当者を主人公にして「日常の課題→解決に至るストーリー」を描くことで、文字だけの資料よりも理解度を高めやすくなります。
さらに、自社サイトの導入事例ページやホワイトペーパーの冒頭にマンガを掲載すれば、読み手の興味を引きつけ、商談前からサービスの強みを把握してもらう効果が期待できます。
活用例3:製造メーカー(BtoC商品PR)
新製品や生活関連商品をPRする場合、SNSでマンガを活用する方法も有効です。
例えば「料理が苦手な主人公が新製品を使って簡単に美味しい料理を作れるようになる」といったストーリーを描けば、利用シーンをイメージしやすくなり、InstagramやX(旧Twitter)などでの保存やシェアにつながります。
また、キャンペーン期間中にECサイトと連動させれば、新規購入者の獲得促進や「使ってみたい」という動機付けにもつなげられるでしょう。
活用例4:一般企業(採用活動)
採用活動においては「会社の雰囲気」や「社員の一日」をマンガ化する活用方法があります。
パンフレットや説明会では伝わりにくい職場の空気感や働くやりがいを、ストーリー仕立てで表現することで、学生や求職者の共感を得やすくなります。
特に就職活動中の若年層はSNSやマンガに親しんでいるため、親近感を持たれやすく、エントリー数の増加や説明会への参加意欲向上といった効果が期待できます。
このように、マンガは BtoB・BtoCを問わず幅広い業種で活用できる可能性があり、理解促進・共感獲得・行動喚起を同時に実現できる手段 といえます。
【Souki流 マンガ導入4ステップ】
当社では、以下の導入ステップを踏むことでより目的や成果にこだわるマンガ制作が可能です。
- 目的の明確化
何を伝えたいか(商品説明/採用活動/ブランディング)を決める - ターゲット設定
誰に読ませるか(顧客/求職者/社員)を絞る - シナリオ設計
ストーリー展開やキャラクター設定を構築
「問題提起 → 解決策提示 → 行動喚起」の流れを作る - 制作・活用
プロに依頼して制作
Webサイト・SNS・紙媒体など複数チャネルで配信
マンガ導入のプロセス図
上記のプロセスを表にまとめてみました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 目的の明確化 | 伝えたいことを決定 | 例:サービス理解促進、採用強化 |
| 2. ターゲット設定 | 誰に届けるかを決定 | 顧客・求職者・社員など |
| 3. シナリオ設計 | ストーリー展開を構築 | 問題提起 → 解決策提示 → 行動喚起 |
| 4. 制作・活用 | 制作&チャネル展開 | Web・SNS・紙媒体で多角展開 |
マンガ制作の流れ
納品までの流れは以下の通りになります。
完成までのおおよその期間は、1~2か月程度となります。(時期や受注状況による)
1,ヒアリング 企業の強みや訴求ポイント、ターゲット層を明確化。
2,シナリオ作成 ユーザーの課題解決ストーリーを構築。
3,ネーム(コマ割り案)提出 流れやセリフを確認できる段階。
4,作画・着色 ターゲットに合わせたテイストで仕上げ。
5,納品・活用 WEB用・SNS用など、媒体ごとに最適化して納品。
制作依頼時のチェックポイント
- ターゲット層に合った絵柄・作風を得意としているか
- マンガ制作の事例や実績があるか
- SNSやWEBに最適化された形式で納品できるか
- 著作権や二次利用について問題ないか
価格だけで判断するのではなく、長期的に活用できるクオリティを重視することが大切です。
### マンガ制作に関するよくある質問
**Q1. マンガ制作にはどれくらいの期間がかかりますか?**
A. 通常は1~2か月程度で完成します。内容の複雑さや修正回数によって前後します。
**Q2. 制作費用の目安はどのくらいですか?**
A. ページ数や作画テイストによって異なりますが、数十万円規模からスタート可能です。長期的に活用できるクオリティを重視することをおすすめします。
**Q3. どんな業種でもマンガ制作は効果がありますか?**
A. はい。BtoB・BtoC問わず、サービス説明・商品PR・採用活動・社内教育など幅広い用途で活用可能です。
**Q4. SNSでも活用できますか?**
A. もちろんです。InstagramやX(旧Twitter)などでは拡散性が高く、広告色を抑えたストーリー形式は自然にシェアされやすいです。
**Q5. 納品形式はどのようになりますか?**
A. Web用・SNS用・印刷用など、利用シーンに合わせた形式で納品可能です。
まとめ:マンガ制作導入のポイント3つ
マンガ制作で成果を出すための3つのポイント
1. 目的を明確にする
(商品PR/採用活動/ブランディングなど、何を達成したいかを最初に決める)
2. ターゲットを絞る
(顧客・求職者・社員など、誰に届けたいのかを明確化する)
3. ストーリーと活用チャネルを設計する
(シナリオ設計+Web・SNS・紙媒体など複数チャネルで展開すると効果が最大化)
→ マンガは「理解促進」「共感獲得」「行動喚起」を同時に実現できる、強力なマーケティング手法です
最後に
WEBサイトやSNSでの集客やブランディングに課題を感じている企業にとって、マンガ制作は強力な選択肢の一つです。直感的にわかりやすく、感情に訴え、拡散性も高いため、広告や記事に比べてユーザーの心に残りやすい表現方法といえます。
実際にIT業界・製造業・一般企業の採用活動など幅広い分野で成果が出ており、用途は商品PRから採用活動、さらには社内教育まで多岐にわたります。
発注企業としては、単なる「面白いコンテンツ」としてではなく、「自社の商品やサービスを正しく理解してもらい、最終的な行動につなげるマーケティング施策」としてマンガを位置づけることが重要です。
もし「文章では伝えきれない」「競合と差別化したい」という悩みがあれば、マンガ制作の導入を検討してみる価値は十分にあるでしょう。
このブログを書いた人
WEB関連に携わって20年越え。ECサイトの運営からスタート。
ホームページ制作に携わって、15年以上になります。