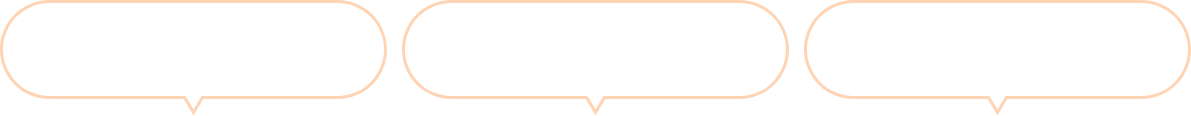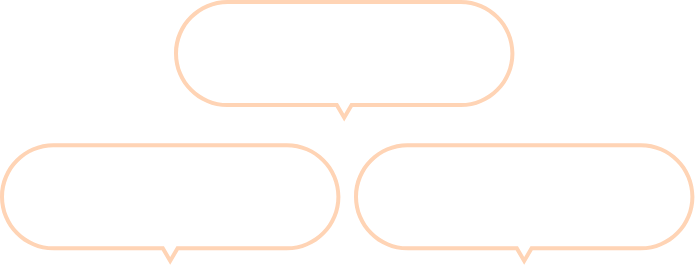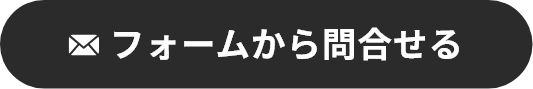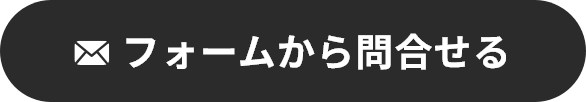製造業のホームページ制作で大事なこと
2025/10/23
Contents
~見込み客に選ばれる「営業型サイト」への転換~
製造業ホームページの役割は「営業ツール」へ
かつて製造業のホームページは「会社案内」的な役割が主でした。
しかし、近年では展示会や紹介頼みの営業だけでは新規顧客を獲得できない時代に変化しています。
発注担当者の多くは、商談前にネット検索で候補企業を調べます。つまり、「検索段階で比較・検討が始まっている」のです。
そのため、製造業のホームページはもはや会社案内的な役割ではなく、営業担当者の代わりに見込み客へアプローチする営業ツールでなければなりません。
では、「製造業のホームページ制作するのに大切なこと」とは何なのか。製造業のホームページ制作で大事なポイントについて解説していきます。
大事なポイント①:技術力より「分かりやすさ」
製造業の方がよく陥るのが、「専門用語が多すぎて伝わらない」ことです。
専門性の高さは強みですが、発注側の担当者が同じレベルの知識を持っているとは限りません。また、サイトを見るのは発注を検討しているクライアントだけではありません。
求職者が閲覧した場合はどうでしょうか。発注側の担当者と同じように、専門用語が多く、どういったことを製造しており、社会にどう貢献できるのか、自分のスキルを活かせるのかが伝わりません。
大事なのは、「誰に」「何を」「どのように」提供できるかをわかりやすく言語化することです。
例)
- 悪い例「高精度なNC加工によるミクロン単位の品質保証」
- 良い例「試作品1個からでも高精度に仕上げ、短納期対応できます」
「読む人の立場に立った表現」ができるかどうかが、問い合わせ数を左右します。
そこに「なるほど」「ここなら安心できそう」と思える表現があれば、問い合わせも応募も自然と増えていきます。
つまり、技術を語る前にまず「伝え方」を設計すること。
それが、営業面でも採用面でも成果を出すための第一歩です。
大事なポイント②:信頼感を生む情報設計
BtoBの製造業サイトでは、「信頼できる会社かどうか」が判断基準になります。
特に、初めて取引する企業は慎重に見ます。だからこそ、以下の情報を明確に掲載することが大切です。
- 製造実績・導入事例
- コラムやブログで情報発信(専門的な情報をわかりやすく具体的に説明)
- 会社概要・沿革(創業年や実績年数)
- 設備一覧・写真(対応可能な加工範囲を具体的に)
- 主要取引先・導入実績(社名非公開でも業種などで表現)
- 品質管理体制・検査機器の紹介
- スタッフ紹介(人が見える安心感)
見込み客は「この会社なら任せても大丈夫そうだ」と思った瞬間に、問い合わせボタンを押します。
つまり、おしゃれで洗練されたデザインよりも、信頼性を感じさせる情報の整理が重要です。
大事なポイント③:課題解決への期待
製造業のホームページでは、「顧客の課題をどう解決できるか」を明確に伝えることが重要です。単に技術力を紹介するだけでなく、課題に対してどのようなアプローチで解決したのかを示すことで、信頼性が高まります。
そのためには、「課題別の解決事例」ページを設けるのがおすすめです。
たとえば「コスト削減」「品質改善」「短納期対応」など、テーマごとにカテゴリーを分けて紹介すると効果的です。これにより、訪問者は自社の課題に近い事例を見つけやすくなり、問い合わせにつながりやすくなります。
大事なポイント④:スマホ対応とUI改善
製造業サイトでも、閲覧の約50%がスマホからというケースは珍しくありません。
特に発注担当者が出張中や現場で確認するケースも増えています。
スマホ対応(レスポンシブデザイン)は必須です。
また、製品情報や加工事例を探しやすくする「導線設計(UI)」も重視しましょう。
- メニューをシンプルに
- 「技術・設備」「製品事例」「会社情報」などのカテゴリーを整理
- お問い合わせボタンは常に画面内に表示(固定)
- カタログやPDFダウンロードでリード獲得を促す
デザインはシンプルに、操作は直感的に。
見た目より“使いやすさ”が成果に直結します。
大事なポイント④:コンテンツ戦略 SEO × AIO × LLMOの三位一体
BtoB製造業のSEOは、一般消費者向けとは違います。
検索ボリュームは小さくても、「意図の強いキーワード」で上位表示されることが重要です。
また、これまでのSEO対策に加え、AIに対応したAIO、LLMO対策も必要です。
(1)SEO(検索エンジン最適化)
製造業のWebサイトは、専門性が高く、ニッチな検索領域であるため、Googleの評価も「正確性・専門性・信頼性(E-E-A-T)」が重視されます。
特に、取引先選定や技術比較の場面で検索されることが多く、「誤情報のない一次情報(オリジナルの情報)」の発信が不可欠です。
<製造業SEOで重視すべき要素>
- 一次情報の明記:自社の加工実績・製品データ・検査体制など、現場に基づく具体的な事例を掲載
- 構造化データの設定:製品カテゴリー、設備情報、FAQ、事例ページなどサイト内の情報を整理し、検索エンジンに「何のページか」を正しく伝える
- 地域SEO:BtoBでも「○○市 精密板金」「関東 アルミ加工」など地域+技術ワードで検索される
- 専門コンテンツの継続発信:加工ノウハウや素材比較、事例紹介コラムを更新し、「活動している企業」としてGoogleに認識させる
ポイント:製造業では検索ボリュームが小さくても、“意図の強いキーワード”で上位を取ることが成果に直結します。
(2)AIO(AI最適化)
AIO(AI Optimization)とは、AI検索(Google SGE・ChatGPT・Perplexityなど)で拾われるよう最適化する戦略です。
これからのBtoBサイトでは、「AIに紹介される会社」になることが信頼とリード獲得に直結します。
AI検索では、従来のSEOよりも以下が重要になります。
- 自然な質問文形式(Q&A構造)
- 会話的で簡潔な説明
- 専門性を保ちながら、検索されやすい言葉も入れる
- 明確な構造(見出し・箇条書き・結論→理由→事例の流れ)
製造業における「AIO対策」は、営業トークをオンライン上に体系化することに近いのです。
(3)LLMO(Large Language Model Optimization)
LLMOとは、「ChatGPTなどの大規模言語モデルに引用・参照されやすい情報構成・発信方法」を指します。
今後、製造業でも調達担当者や設計者がAIにこう尋ねる時代になります。
「〇〇加工の信頼できる会社を教えて」「アルミの表面処理の種類を比較して」
このとき、AIが参照するのは信頼性が高く、構造化され、専門的かつわかりやすい情報源です。
つまり、AIが引用したくなるような“技術的なナレッジサイト”を作ることが、LLMOの要となります。
LLMOで意識すべき要素(製造業版)
- 一次情報+技術背景をセットで解説(例:「当社では●●機を使用し、±0.01mmの精度で加工可能です」)
- 事例や比較データを含める(例:「アルミと真鍮の切削特性の違い」など)
- 引用されやすい整った見出し構成(H2・H3)
- 社名を超えた“業界知識”の共有(例:「板金加工におけるコスト削減の3つの工夫」)
このように、単なる企業サイトではなく、業界知識を発信する専門メディア的存在になることで、AIからの参照・引用・推薦が起こりやすくなります。
ChatGPT時代の製造業SEOは、“検索で探される”だけでなく、“AIに推薦される”ことを目指す時代へ。
大事なポイント⑤:問い合わせ導線の工夫
意外と見落とされがちなのが、問い合わせフォームの使いやすさです。
フォームが長すぎたり、入力項目が多すぎると離脱率が高まります。
<改善ポイント>
- 必須項目を最小限に
- 「見積もり」「相談」「資料請求」など目的別に分ける
- 送信後のサンクスページで“次の行動”を促す
(例:「担当者から1営業日以内にご連絡します」など)
BtoBでは「すぐ聞きたい」というニーズが強いため、複数の問い合わせ手段を用意するのが効果的です。
大事なポイント⑥:採用ページとの連動
ホームページは営業だけでなく、採用にも大きく関わります。
製造業では若手採用が難しい中、「どんな会社か」がわかるコンテンツは応募率を大きく左右します。
<採用ページの構成一例>
- 社員インタビュー
- 現場写真・工場の雰囲気
- 教育制度・キャリアパス
- 社内イベントや地域との関わり
営業ページとトーンを統一し、「働く人」「つくる人」の魅力を伝えることで、取引先にも「誠実な会社」という印象を与えます。
FAQ
Q1. 自社で更新するのが不安です。どうすればよいですか?
A. WordPressなどのシステムを使って、ブログ更新やお知らせ投稿を簡単に社内で更新することができます。更新しやすい設計にすることが重要ですので、制作依頼前に一度、相談することをおススメいたします。
Q2. SEO対策は制作会社に任せれば十分ですか?
A. 技術的なSEOは任せてもよいですが、「どんなキーワードで見つけられたいか」は自社が明確にする必要があります。現場を知る営業や技術者の知見が最も効果的です。
Q3. デザインより中身を重視した方がいいですか?
A. はい。もちろん伝えるためにはデザイン性も重要です。しかし、「おしゃれで洗練されたデザイン」よりも「信頼性」「分かりやすさ」「正確な情報」が優先されます。
制作実績
まとめ
製造業のホームページ制作で大事なのは、「自社を正しく・わかりやすく・信頼感を持って伝える」ことです。
見た目だけでなく、情報設計・導線・コンテンツ戦略・更新体制までをトータルで考え、「営業に強いサイト」に育てていくことが成果への近道です。
このブログを書いた人
WEB関連に携わって20年越え。ECサイトの運営からスタート。
ホームページ制作に携わって、15年以上になります。