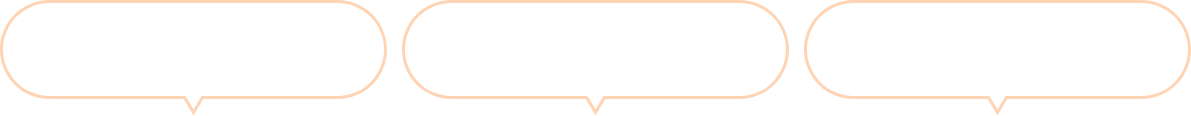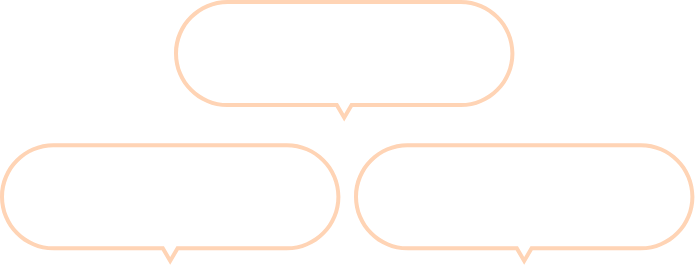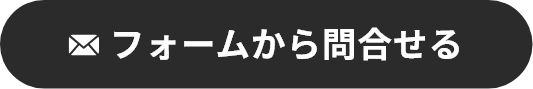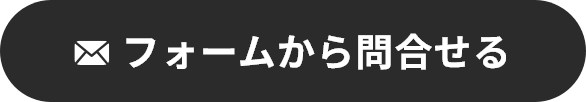テンプレート制作 vs オリジナル制作
2025/10/06
Contents
はじめに:なぜ「テンプレート制作 vs オリジナル制作」は重要な選択か
ホームページ(WEBサイト)は、企業・サービス・ブランドの「顔」として機能します。
そのため、「どう見せるか」「何を伝えるか」「どう動線設計するか」はビジネス成果に直結します。
しかし一方で、予算やスケジュール、制作リソースに制限があることも多く、「テンプレートを使うべきか」「オリジナルで作るべきか」は悩みどころです。
本稿では、テンプレート制作とオリジナル制作の特徴・メリット・デメリットを整理し、用途・目的別に最適な選択肢を示したうえで、判断のための視点を提案します。
結論
- 集客が目的であり、将来的な拡張性なども考慮するならオリジナル制作
- コーポレートサイトなど名刺代わりのサイトを早く制作したい場合(1か月以内)は、テンプレート制作
- ステップ型として、創業時はテンプレート、集客を行う段階でオリジナル制作
- ハイブリッド型としては、テンプレート型だが主要ページはオリジナルにて制作
- 現在は、どちらもモバイルファースト(スマホ対応)には対応している。
- 最適解は「自社条件に即した選択」
テンプレート制作とは/オリジナル制作とは
テンプレート制作(テンプレート型/既成デザインベース)
テンプレート制作とは、予め用意されたデザインテンプレート(テーマ、雛型)をベースに、画像・テキスト・配色などを差し替えて仕上げる方法を指します。
テンプレート型は、制作会社やCMS・ウェブサービス提供者側がテンプレートを複数用意しておき、クライアント(依頼者)はその中から選び、最小限のカスタマイズで制作を進めます。
特徴として、レイアウト構造そのものの変更は難しい、あるいは制限されることが一般的で、自由度はテンプレート設計側に依存します。
オリジナル制作(オリジナル型/フルオーダー制作)
オリジナル制作とは、ゼロベースでデザイン設計・構成設計し、要望や事業戦略、ブランドイメージに合わせてページ構造や機能・動線も含めてカスタム設計する方式です。フルオーダーとも呼ばれます。
この方式では、要件定義 → デザイン → コーディング → テスト → 調整 の流れ、すべてにおいて柔軟性を持たせられるため、ブランドの世界観や差別化、ユーザー体験(UX/UI)の最適化を追求できます。
両者のメリット・デメリットを比較
以下に、テンプレート制作とオリジナル制作の主なメリット・デメリットを比較して整理します。
| 項目 | テンプレート制作 | オリジナル制作 |
| 初期コスト | 低め。既存デザインを流用できるため、設計・デザインコストを抑えやすい | 高め。ゼロから設計・開発するため、時間と労力がかかる |
| 納期(制作期間) | 短い。テンプレート活用でデザイン設計工数を削減できる | 長め。要件確認・調整・修正プロセスが発生しやすい |
| 自由度・柔軟性 | 制限あり。構成・レイアウト・細かい表現の変更が難しいことも多い | 高い。ブランドイメージ・機能要件・ユーザー導線などを詳細に設計可能 |
| 差別化/オリジナリティ | 弱め。他社も同テンプレートを使う可能性があるため、似たデザインになりやすい | 強め。独自性のあるデザイン・ストーリーを反映でき、ブランドとしての識別性が高まる |
| 改修・拡張性 | 制限が出やすい。テンプレートの仕様に従う必要があり、変更・追加時に制約を受けることがある | 柔軟。将来的な拡張や改修を見据えた設計ができる |
| SEO/パフォーマンス | テンプレートによっては不要なコードやデザイン要素を含むことがあり、軽量化・最適化が不十分なケースもある | 最適化を前提に設計できるため、読み込み速度・構造化マークアップ・SEO要件を反映しやすい |
| 初期設計・要件定義 | 比較的シンプル。要求仕様が限定的で済む場合が多い | 入念なヒアリング・要件定義が必須。方向性やブランド価値を言語化する必要あり |
目的別に考える「どちらを選ぶべきか」
テンプレート制作/オリジナル制作、どちらを選ぶかは、目的やフェーズ、予算・時間などの条件によって変わります。以下、主なケース別におすすめを示します。
ケース 1:とにかく早くローンチしたい、まずは実績を作りたい
- 起業直後、プロトタイプ段階など、最小限のコストで「まず形にしたい」フェーズなら、テンプレート制作が適切です。
- とりあえず業務案内ページや問い合わせ先を設けたい、名刺代わりのサイトで十分という場合など。
注意点:テンプレートを使ったとしても、ブランドの一貫性を保つため、画像や文言、カラーなどにはこだわるべきです。また、差別化要因があるなら訴求すること。ブログ・コラムの投稿ができれば更新を継続するのがベスト(リニューアル時に移管できるか要確認)。
ケース 2:ブランディングを重視・中長期で育てていきたい
- 事業が安定してきて、他社との差別化が不可欠な段階。
- ブランドの世界観(ミッション・ビジョン・価値観)をデザインに反映させたい。
- コンテンツや機能が増える見込みがあり、将来的にサイト構成を自在に変えたい。
こういった条件が揃うなら、オリジナル制作のほうが後悔しない選択となります。
ケース 3:中間的な選択肢・ハイブリッド戦略
- テンプレートをベースに、主要ページ(トップページ・商品紹介ページなど)だけをオリジナル設計する。
- カスタマイズ性の高いテンプレートを選び、必要な部分だけ設計を入れる。
- 初期はテンプレートでリリースし、後段でオリジナル改修を入れる段階戦略を取る。
- ブログ・コラムによりユーザーに情報提供することで、サイトボリューム(サイトのページ数)を稼ぐ。
このように段階を踏むことで、初期投資を抑えつつ、将来的な改修性を担保できるケースもあります。
判断のためのチェックリスト・視点
以下の観点をもとに自社に適した方向を判断するとよいでしょう。
- 予算とリソース(時間・人員)
予算が絞られている/急ぎのスケジュールならテンプレート有利。ただし「安さだけ」で選ぶと後のコストがかかるリスクも。 - 目的・期待効果
サイトを通じた集客を重視するか、信頼感やブランド向上を重視するかで要件が変わる。 - 差別化要件
競合サイトとの差別化が必須かどうか。差別化が必要ならオリジナル要素は必須。 - 将来拡張性
将来的に機能追加や構成変更を見込むなら、柔軟性を持たせられる制作方式が望ましい。 - 運用体制・管理性
運用担当者がデザイン・コードの知識を持っていないなら、過度なカスタマイズより管理しやすさを重視すべき。 - SEO・パフォーマンス要件
軽量化、最適化、構造化マークアップなどを重視するなら、設計段階で最適化できるオリジナル型が優位。 - ブランド価値・世界観表現
ブランドのストーリーや個性を反映させたいなら、デザイン自由度が高いオリジナルが望ましい。
成功に導くポイント・注意点(SEO/LLMOも意識して)
せっかく制作するなら、成果に繋がるサイトにしたいはずです。以下は、どちらの方式でも意識しておきたい成功のポイントです。
キーワード設計(SEO要件)を先に定める
サイトの目的・ターゲット層に応じたキーワード選定を先行させ、それを元に構造や見出し設計を行うこと。
UX/UI 最適化と導線設計
見た目のデザインだけでなく、ユーザーが迷わず目的(問い合わせ/購入など)にたどりつける動線を設計することが重要。
モバイルファースト設計
スマートフォンでの閲覧性・操作性を優先した設計。特にテンプレート型はモバイル対応が不完全なものも中にはあるので確認すること。
読み込み速度の最適化
画像の最適化・スクリプトの遅延読み込み・キャッシュ制御などを取り入れ、ページの表示速度を意識すること。
余計なコード・不要なプラグインを減らす
特にテンプレート利用時、不要な機能やプラグインを残したままだとパフォーマンス低下やセキュリティリスクが生じることも。
コンテンツ戦略と更新性
ブログ・お知らせ・事例紹介などを定期的に更新できる体制をつくること。CMSを導入するなら、編集性・拡張性を重視する。
テストとレビュー、改善サイクル
公開前のデバイスチェック(PC・スマホ・タブレット)やユーザー視点の検証を怠らず、公開後もアクセス解析に基づく改善(PDCAサイクル)を繰り返すこと。
将来改修を見据えた設計
最初から「将来こういうページを追加したい」「機能を変えたい」といった計画を盛り込む余裕を持って設計すること。
まとめ:最適解は「自社条件に即した選択」
テンプレート制作とオリジナル制作には、それぞれ一長一短があります。
「どちらが絶対に良いか」ではなく、自社の目的、予算、リソース、成長戦略に最適なバランスで選ぶことが肝要です。
- スタート段階・予算制約があるなら → テンプレート型+必要な要所のみオリジナル要素を入れるハイブリッド戦略
- 成熟期・ブランディング強化・将来的拡張を視野に置くなら → オリジナル制作を前提に設計を入念に
- 中長期視点での回収(投資対効果)を意識し、最適化・運用を前提とした設計を重視する
このブログを書いた人
WEB関連に携わって20年越え。ECサイトの運営からスタート。
ホームページ制作に携わって、15年以上になります。