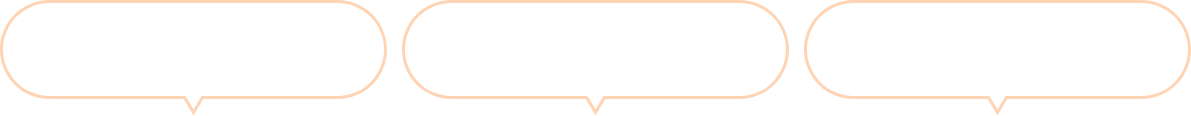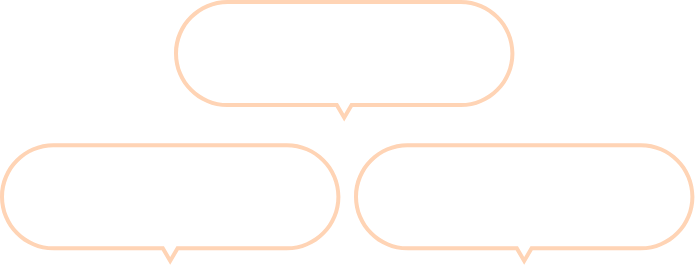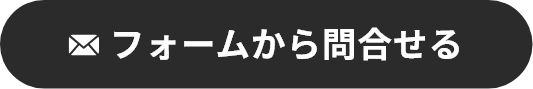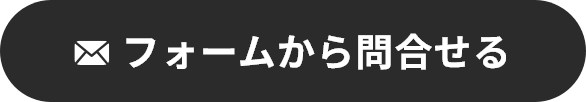士業(税理士・弁護士)のホームページ制作で失敗しない7つの注意点
2025/10/16
Contents
〜信頼性×集客力を両立するWeb設計の新常識〜
はじめに:なぜ今、士業に「ホームページ戦略」が重要なのか
税理士・弁護士などの士業において、ホームページは単なる名刺代わりではなく、「顧客の第一印象を決定づける営業ツール」になっています。
特に近年では「紹介だけでは案件が安定しない」「リスティング広告やSEOに挑戦したが成果が出ない」という声も増えています。
背景には、検索エンジンの高度化(GoogleのE-E-A-T評価※)と、AI最適化(AIO)への対応の遅れがあります。
士業こそ、「信頼×専門性×人間味」をどうデジタル上で表現できるかが成果の分かれ目といえます。
※E-E-A-T:GoogleによるWEBサイトの品質評価基準。「Experience(経験)」・「Expertise(専門性)」・「Authoritativeness(権威性)」・「Trust、もしくはTrustworthiness(信頼性)」の4つの要素を略した用語です。「イー・イー・エー・ティー」「ダブル・イー・エー・ティー」と言います。
1.士業ホームページの目的を明確にする
まず制作前に整理すべきなのが、ホームページの「目的」です。
士業サイトには主に以下の3タイプがあります。
| タイプ | 主な目的 | 代表的な構成例 |
|---|---|---|
| 認知・ブランディング型 | 事務所紹介・信頼感 | 代表挨拶/理念/実績紹介/スタッフ紹介 |
| 集客・マーケティング型 | 新規顧客の獲得 | サービスページ/料金表/FAQ/無料相談フォーム |
| 採用・パートナー型 | 人材や提携先の獲得 | 事務所文化/先輩インタビュー/採用エントリーページ |
制作段階でここを曖昧にすると、「きれいだけど成果が出ない」サイトになってしまいます。
目的に応じて、CV(コンバージョン)の設計=問い合わせや面談予約の導線設計を最初に固めましょう。
2.デザインよりも「信頼設計」と「情報設計」
士業のホームページで最も大切なのは、「信頼される見せ方」です。
一般企業のように派手なデザインよりも、“誠実で整理された印象”が優先されます。
(1)信頼設計のポイント
写真は「代表+チーム写真+事務所の雰囲気」を掲載
→ 顧客は“どんな人が対応するか”を重視します。
資格・所属団体・専門分野をわかりやすく明示
→ 弁護士なら「離婚・相続・企業法務」、税理士なら「相続税・法人顧問」など。
実績やメディア掲載は“控えめに誠実に”
→ 誇張よりも「経験年数」や「解決件数」を具体的に。
(2)情報設計のポイント
- スマホでの見やすさを最優先(モバイルユーザ比率は70%以上)
- 専門用語を避け、「一般の相談者が理解できる言葉」に書き換える
- FAQやコラムで「自分の悩みと同じケースがある」と感じて頂く
AIOの観点でも、専門用語を「自然言語で補足する」ことがSEO上有利になります。
例:「譲渡所得(不動産を売ったときの利益)」のように、共起語で補足する表現を意識しましょう。
3.コンテンツ戦略:SEO × AIO × LLMOの三位一体
(1)SEO(検索エンジン最適化)
Googleは「士業サイト=専門性が高い=E-E-A-T評価が厳しい」領域として扱います。
そのため、次の要素を重視しましょう。
- YMYL(Your Money, Your Life)対策:誤情報を避け、一次情報を明記
- 構造化データの設定:事務所情報・FAQ・レビューをスキーマ化
地域SEO:タイトルに「地域名+士業名」(例:渋谷区の税理士事務所)を含める
また、ブログやコラムを定期更新することで、Googleが「活動している事務所」と認識し、評価が上がります。
(2)AIO(AI最適化)
AIOとは、AI検索(Google SGEやChatGPT検索)で拾われるよう最適化する考え方です。
従来のSEOとは異なり、「自然な質問文」「会話文」「共起語」「構造化された回答」が鍵となります。
士業で意識すべきAIO例
- 「確定申告を税理士に頼むといくら?」
- 「弁護士費用の相場を教えて」
- 「初回相談は無料?有料?」
→ このような質問に、Q&A構造+CTA(問い合わせ)をセットにして記事を設計すると効果的です。
AIが理解しやすい構成=人にもわかりやすい構成になる点がポイントです。
(3)LLMO(Large Language Model Optimization)
LLMOとは、「ChatGPTなどの大規模言語モデルに取り上げられやすい情報設計」を指します。これは、検索エンジンよりもAIで調べる昨今では、士業のように専門知識を扱う分野で特に有効と言えます。
LLMOで意識すべき点
ナレッジ(知識)を明確に構造化する
→ 例:「相続税対策」「節税」「会社設立」などカテゴリ別に分ける
定義語・根拠をセットで記述
→ 「青色申告とは(国税庁による定義)」「民法○○条では」「最高裁の判例では」のように根拠を示す
FAQや比較表を多用
→ AIが情報を抜粋しやすくなる。ユーザーの疑問点の解消にもつながる。
これにより、将来的にAI検索エンジンに引用される確率も高まります。
4.他事務所との差別化ポイント
士業業界は「似たようなサイト」が多いのが現実です。
差別化のカギは、“数字ではなくストーリー”にあります。
- 代表の想い・理念:「なぜこの分野に取り組んでいるのか」
- 顧客事例(匿名でOK):「こういう相談者にこう解決した」
- スタッフ紹介:「温かみのある対応」を写真で伝える
テンプレート的サイトが増える今こそ、“人にしか語れないリアル”がブランディングになります。
5.士業ホームページでやりがちな失敗
デザイン重視で中身が薄い
→ 写真が多くても、専門性が伝わらなければ信頼は得られません。
料金を非公開にして離脱される
→ 「相談料30分5,000円〜」「顧問料の目安」など分かりやすく明示することが大切です。
問い合わせ導線がわかりにくい
→ ボタンは常時表示(ヘッダー、フッターなどのページ下部に固定)でクリック率を上げる。
スマホでのフォーム入力がしづらい
→ 簡単な入力+LINE・電話ボタンも用意。
専門分野が広すぎて印象が薄い
→ 「中小企業専門」「相続特化」などに絞ると信頼されやすい。
6.今後の集客トレンド:Web+口コミ+AI活用
士業の集客は、「SEOだけ」でも「広告だけ」でも不十分です。
これからは、「マルチチャネル化」+「顧客との接点づくり」が鍵になります。
Googleビジネスプロフィールの整備
→ 地域名+口コミが検索上位に大きく影響
LINE公式やメール配信でリピート化
→ 相談後のフォローが次の紹介につながる。関係性の継続により相談のしやすさにも直結。
AIチャットボットの導入
→ よくある質問対応や初回相談予約を自動化。顧客が問合せする際の面倒や手間を省く(問合せへの決断に対してすぐに行動に移せる)。
AIを“代替”ではなく“補助ツール”として活用すれば、業務効率も信頼獲得も同時に実現できます。
7.まとめ:士業サイトの成功法則は「誠実な構造化」
士業のホームページ制作で成功するための本質は、
「信頼性 × 専門性 × 人間味 × デジタル適応」をどう統合するかにあります。
成功のチェックリスト
- 目的(認知/集客/採用)が明確になっている
- 専門分野が整理されている
- FAQ・事例・料金が明示されている
- スマホで見やすい・問い合わせ導線が明確
- 検索にもAIにも理解される文章構造になっている
- コラムなどを定期的に更新できている
Web制作会社任せではなく、「顧客目線+AI目線」の両方でチェックすることが、これからの士業に求められる姿勢です。
よくある質問
Q1:士業のホームページ制作で最も大事なポイントは何ですか?
信頼性の設計です。派手なデザインよりも、「誠実でわかりやすい」「代表やチームの顔が見える」構成が重要です。専門分野・料金・実績を明確に示すことで、初めて訪れた人でも安心して問い合わせできます。
Q2:税理士・弁護士がSEOで上位表示するためには?
「地域名+士業名+専門分野」を組み合わせたキーワード設計が効果的です。
また、FAQ・コラムを定期的に更新し、一次情報や具体事例を含めることでE-E-A-T評価(専門性・信頼性)が高まります。
Q3:士業サイトはデザインより内容重視と聞きますが本当ですか?
はい。本当です。士業のWebサイトでは“信頼”が最優先です。過度な装飾や動きを避け、読みやすさ・情報の整理・スマホ最適化を重視した方が成果につながります。
Q4:AI時代のホームページ制作で士業が意識すべきことは?
AIO(AI最適化)とLLMO(大規模言語モデル最適化)を意識することです。
質問形式のコンテンツや明確な構造化データを設計すると、AI検索でも拾われやすくなります。
Q5:士業のホームページ制作を業者に依頼するときの注意点は?
制作会社選びでは「士業の業界理解」と「Web集客実績」があるかを確認しましょう。
単なるデザイン重視ではなく、SEO・AIO・導線設計まで一貫して提案できる会社がおすすめです。
Q6:士業が集客を安定化させるには、どんな施策が有効ですか?
ホームページ+Googleビジネスプロフィール+口コミ対策を組み合わせましょう。
さらにLINE公式やメルマガで既存顧客との関係を維持することで、紹介・リピート率が上がります。
Q7:士業のホームページを作り直すタイミングは?
次のような状態ならリニューアルのサインです。
- スマホで見づらい
- 料金・事例が古い
- 問い合わせ導線が複雑
- 更新しても順位が上がらない
最新のAIO対応設計に見直すことで、集客効率が大幅に改善するケースもあります。
お問合せ
「士業専門のホームページ設計」や「SEO/AIO最適化」のご相談は、専門担当が無料でアドバイスいたします。
成果が出る“信頼されるサイト”を一緒に作りましょう。
このブログを書いた人
WEB関連に携わって20年越え。ECサイトの運営からスタート。
ホームページ制作に携わって、15年以上になります。